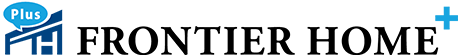- よ
-
容積率
容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対し建築物の延べ面積が占める割合のことをいいます。
容積率の値は建築基準法に基づいて用途基準が定められ、その用途地域の区分に応じて決められています。
「容積率=延床面積(床面積の合計)/敷地面積」
つまりその敷地に対してどれくらいの規模の建物が建てられるかという割合のことで、用途地域ごとに制限されています。都市計画上、空間を有効活用することや、良好な市街化形成を図ることを目的として規定されています。
例えば敷地面積が60m2で容積率が150%の場合は延床面積すなわち1階2階の床面積の合計(延床面積)で90m2建てることが可能です。
例えば、1階床面積45m2、2階床面積45m2の建物が建築可能となります。
この「容積率」の数値が大きいほど、大きくて広い建物が建築可能です。
住居系の用途地域は容積率が低く、商業系の用途地域は容積率が高くなっています。大きいビルや高いビルなどは、ほとんどの場合商業地域に建築されています。
また、容積率は都市計画によって定められた最高限度のほかに敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合、その幅員によっても制限があります。
住居系の用途地域の場合、前面道路の幅員のメートル数に0.4を掛けた割合、その他の用途地域の場合、前面道路の幅員のメートル数に0.6を掛けた割合以下でなければなりません。
用途地域ごとに都市計画で定められた割合と、前面道路の幅員により計算された割合のうち小さい方がその敷地の容積率となります。その土地に定められた容積率・建ぺい率をみれば、その土地にどのような住宅が建設できるかがわかります。
もうひとつの建ぺい率とは「敷地面積に対する建築物の建築面積の占める割合」を定めたものです。
詳しくは不動産用語集「建ぺい率」ページへ<参考>用途地域別 建ぺい率・容積率一覧表 用途地域 建ぺい率 容積率 第一種低層住居専用地域 30、40、50、60%のうち
都市計画で定める割合50、60、80、100、150、200%のうち
都市計画で定める割合第二種低層住居専用地域 30、40、50、60%のうち
都市計画で定める割合50、60、80、100、150、200%のうち
都市計画で定める割合第一種中高層住居専用地域 30、40、50、60%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合第二種中高層住居専用地域 30、40、50、60%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合第一種住居地域 50、60、80%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合第二種住居地域 50、60、80%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合準住居地域 50、60、80%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合近隣商業地域 60、80%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合商業地域 80% 200、300、400、500、600、700、 800、900、1000、1100、1200、1300%のうち
都市計画で定める割合準工業地域 50、60、80%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400、500%のうち
都市計画で定める割合工業地域 50、60%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400%のうち
都市計画で定める割合工業専用地域 30、40、50、60%のうち
都市計画で定める割合100、150、200、300、400%のうち
都市計画で定める割合都市計画区域内で
用途地域の指定のない区域30、40、50、60、70%のうち特定行政庁が
都市計画審議会の議を経て定める割合50、80、100、200、300、400%のうち
特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定める割合 -
用途地域
用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、市街地における適正な土地利用を図るため、その目標に応じて12種類に分け、建築基準法と連動して「建築物の用途」「容積率」「構造」等に関して加えられる一定の制限のことをいいます。
用途地域は、都市計画法によって定められています。用途地域というのは、その場所に建てられている建物の種類や用途などを示し、将来その場所がどんな街並みになるのかをある程度予測させてくれる法律です。
地域によっては、道を一本隔てて用途地域の種類が変わることもあります。建築を計画をする際の大切な目安となります。12の用途地域
- 営業時間:9:00-19:00
- 定休日:火曜・水曜
Fudousan Plugin Ver.1.9.4